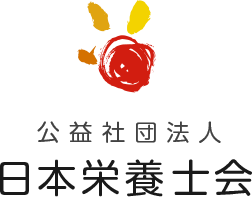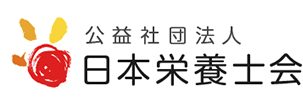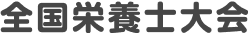栄養と食の専門職であることの周知と、価値観の多様化に適応した指導を目指す
2025/07/01
トップランナーたちの仕事の中身#105
岡本 美千子さん(札幌市立栄西小学校、管理栄養士)

札幌市の小学校で栄養教諭として食育指導や健康課題を有する児童への個別的な相談指導に取り組む岡本美千子さん。急速に変化する価値の多様化の中、栄養と食の大切さを効果的に伝える工夫と個別的な相談指導例について伺いました。
手間を惜しまない学校給食に感動
札幌市立栄西小学校(以下、栄西小学校)で栄養教諭を務める岡本美千子さんが、栄養教諭の道を選んだのは管理栄養士養成校時代の教育実習での経験がきっかけでした。
「教育実習先でラーメンのスープは鶏ガラを煮出し、シチューのルウはバターと小麦粉で手作りするのを見て、これほど手間をかけて給食に取り組んでいるのかと驚き、本当に感動しました。他職域の施設でも実習しましたが、学校給食で受けた感動が忘れられず、管理栄養士として学校給食に取り組むことを決意しました」
就職活動では、当時は栄養教諭制度がなかったために学校栄養職員として入職し、のちに新設された栄養教諭資格を働きながら取得し、札幌市内の小・中学校で28年間勤務してきました。
教科や校内行事と連携した食育授業

現在、岡本さんは栄西小学校で、食物アレルギー対応を含めた給食管理と食に関する指導を主な業務としています。
「食に関する指導は、1~6年の児童全員を対象にしたものと、健康課題を有する児童への個別的な相談指導(以下、個別指導)があります。児童全員への指導は教科時間を使った食育授業、給食時間に校内テレビ放送等の2つを行っています」
取材に訪れた日は6年生のクラスで「適塩のすすめ」と題した食育授業が行われていました。食塩は身体に必要だが、摂り過ぎると良くないことを食品に含まれる食塩量を例に挙げて説明すると、児童たちは「摂り過ぎると生活習慣病の原因になるんだ」等、声を上げて反応していました。
次に朝食、昼食、夕食のモデル献立とそれぞれに含まれる食塩量を見せ、モデル献立が学級担任(以下、担任)の先生の1日の食事だと発表すると「先生、食塩摂り過ぎだよ」等の声が飛び交い、盛り上がりは最高潮に。減塩方法を考える課題が始まると、授業を見守る担任に向けて「ウインナーを4本から2本に減らしたいけどおなかすく?」、「朝食をパンからごはんに変えられる?」等、次々と質問を投げかけていました。 「担任をモデルにすることで適塩の必要性、実行可能な減塩方法が身近な問題に引き寄せられたのだと思います。小学生への指導では、児童の興味関心のある人や物をうまく盛り込むことや、給食の献立と関連させることが理解を深めるきっかけになります。さらに理解度が増すように、教科の学習内容と連携させることも重要です」
教科との連携では、例えば6年生の食育授業で扱う「適塩」は保健体育科の生活習慣病、5年生の地産地消は社会科の食糧生産と連携させるといった具合です。
「4年生の食育授業では、札幌市が平成18年度から取り組んでいる、給食の調理くずや残菜を工場で堆肥化し、それを利用して作物を栽培し、学校給食の食材に用いる『さっぽろ学校給食フードリサイクル』について、社会科のごみと環境の授業と連携させて学びます。教科と連携して学習効果を上げるにはタイミングも大切なため、教科で扱った直後に食育授業が組み込めるように、担任と連携して年間計画を立てています」
もう1つの食の指導である校内テレビ放送は、Power Pointで作成した資料を映像で流しながら説明するというもので、月に2回、給食の時間に行っています。放送時間は食べるのに時間がかかる低学年に合わせ5分と決めています。
「今月は朝食の大切さを効果的に伝えるために、まもなく開催される運動会と関連付けました。運動会の練習真っただ中ですので、朝食を食べて体調を整えることが力の発揮につながると実感できるのではと、期待しています。最近の児童は視覚情報に慣れていて、面白くないと見てくれません。自分の好きなYou Tuberの動画から、構成やテロップの入れ方を参考にすることもあります」
価値観の多様化による指導の変化

給食指導では毎日、給食時間に各クラスを訪問し、ときには声掛けをしながら食事中の変化を見逃さないように心を配りますが、近年の価値観の多様化、SNSの広まりを受けて児童にかける言葉選びには細心の注意を払っているといいます。
「昔は『残さず食べよう』という声掛けが当たり前でしたが、今は『一口だけ食べてみたら』という言葉でも、食べることを強要されたとプレッシャーに感じる場合があるため配慮が必要です。一方で、残すことを極端に嫌がる児童も多くいます。こうした児童はごく少量しか料理を盛らないため、給食の残菜が食べ残しではなく、盛り付けられなかったものが大半になる日もあります。学校給食は発達・発育に必要な栄養を摂り、食の経験を広げる役割があります。食に関する指導はデリケートであることを念頭に置き、時代に適した指導法を模索しています」
平成26年度から実施している札幌市学校教育の柱の1つに健やかな身体の育成があります。
「体育の指導に重点が置かれがちですが、健やかな身体の育成には栄養、休養、運動が必要です。栄養と食事の役割を担任の先生方に知ってもらいたいと考え、月に1回、各学年の先生が持ち回りで開催している『校内ミニ研修会』において学校給食の栄養摂取基準と給食指導を中心にお話ししました」
担任の反応は、給食は栄養満点というイメージは定着しているが、適量に関しての認識は薄い傾向だったといいます。
「この機会に、栄養教諭と担任との指導のすみ分けについても提案しました。栄養管理に関わる指導は栄養教諭が行い、担任は安全に楽しく食事ができる給食時間の確保を行うことを共通理解とすることができたのは大きな前進だと思います」
高度肥満児童に向けた個別的な相談指導
昨年、岡本さんは高度肥満の児童への個別指導にも取り組みました。
「ミニ研修会を開く以前から、食欲旺盛な児童が毎日のように2~3人分の給食をおかわりして食べていることがありました。先生も給食を残すのはもったいないし、食べたい子が食べていいのではと考えていたようです。この児童は入学以来、毎年10㎏以上のペースで体重が増え、高学年になると肥満度80%を超える高度肥満となりました。個別指導の必要性を担任に伝え、担任から保護者に栄養教諭への相談を打診してもらったところ、本人も指導を受けたいとのことで1年間にわたり取り組みました」
発達・発育への悪影響を防ぎ、今後、身長が伸びることを踏まえて体重維持を目標とし、給食は1人分を守り、おかわりしていいのは野菜のおかずと生の果物のみ、家庭では主食の量を計量して食べる等、具体的な改善法を提案しました。また、担任に協力してもらい、休み時間は本人が好きな風船バレーを多く取り入れて楽しく運動できるようにしました。その結果、1年間で体重の増加を抑えることができ、身長は予想どおりに伸びたことで肥満率が低下。それに伴い、膝の痛みの軽減や体力の向上等の変化も見られるようになりました。
「栄養教諭は単独配置が多く、食育授業のスキルアップが止まってしまう恐れがあります。また、食に関する指導には栄養の知識とともに、時代に適したカウンセリング力が求められるようになっています。札幌市の同ブロックの栄養教諭と連携してお互いの食育授業の参観を企画、実施する他、公益社団法人日本栄養士会の研修等を活用してスキルアップを図り、学校における栄養と食の専門職としての周知を広げる努力を続けていこうと思います」
プロフィール:
1997年藤女子大学人間生活学部食物栄養学科卒業後、同年、札幌市の学校栄養職員として札幌市内の小学校に入職。2012年札幌市の栄養教諭に採用され、市内の小学校、中学校に勤務する。2023年より現職。2023年札幌市教育実践功績表彰、2024年文部科学大臣優秀教職員表彰。北海道栄養士会所属。